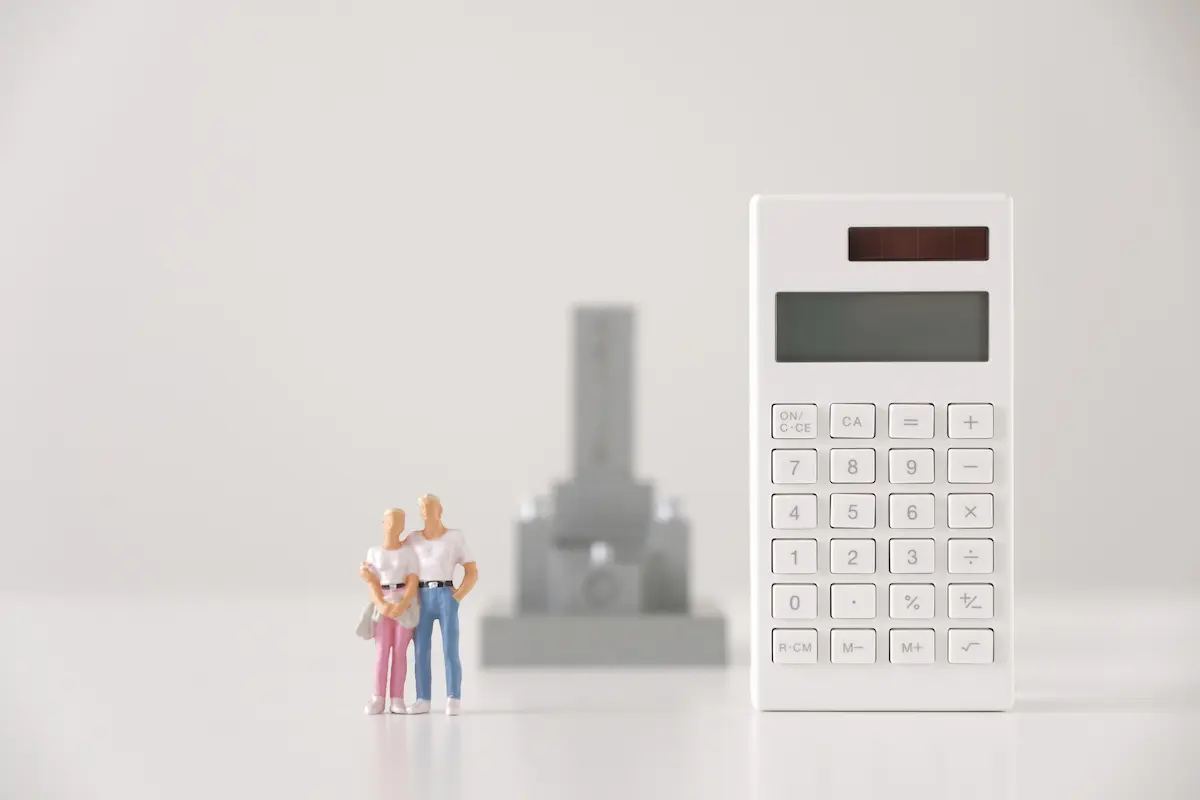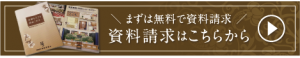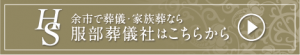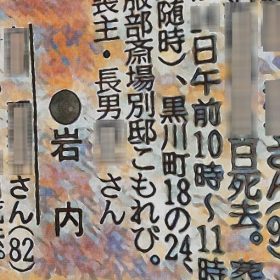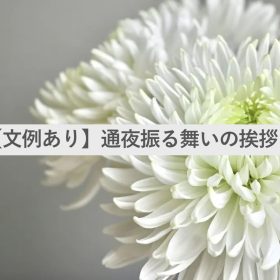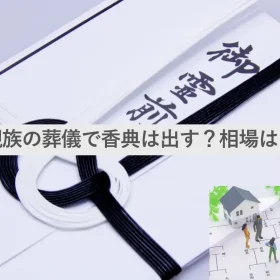親の葬儀について考えるとき、気になるのは「費用がいくらかかるのか」そして「誰がそれを払うのか」ということではないでしょうか。
突然のことで準備ができていない中、喪主や兄弟との関係性、支払い方法、補助金の有無など、悩みは尽きません。実際の費用は、葬儀の形式や地域によって大きく異なり、さらに費用負担をめぐってトラブルになるケースも少なくありません。
この記事では、親の葬儀費用の相場や内訳、誰がどのように負担するべきかの考え方、費用を抑えるポイント、活用できる補助金制度まで、わかりやすく解説します。
これから葬儀を迎える方も、将来に備えたい方も、ぜひ参考にしてください。
目次
親の葬儀費用は誰が払う?負担の考え方と兄弟間トラブルの防ぎ方

喪主が全額負担するとは限らない
親の葬儀費用をめぐって最初に不安になるのが、「喪主になった自分がすべて支払わなければならないのか?」という点ではないでしょうか。
結論から言えば、基本的に喪主が費用を負担するのが一般的です。ただし、法律でそのように定められているわけではありません。喪主はあくまで葬儀をとりまとめる代表者であり、金銭的な責任を一人で背負う立場ではないのです。
実際には、相続人(たとえば兄弟姉妹)全員で費用を分担するのが一般的となっています。ただしそのためには、事前に話し合うことが大切です。また、葬儀費用は急に発生することが多いため、喪主が一時的に立て替え、その後精算するという流れになることもあります。
後から「払ってもらえると思っていたのに誰も動かない…」という事態を防ぐためにも、事前に費用の分担について話し合っておくことがとても大切です。
親の葬儀費用は兄弟姉妹で分担することが可能
親の葬儀費用を誰が払うのかという話になると、「長男が払うべき」「喪主が全部払うもの」など、昔ながらのイメージで決めつけられることがあります。
しかし現在では、兄弟姉妹などの相続人全員で分担するのが一般的です。法律上の明確なルールはありませんが、以下のような分担方法が多く見られます。
- 相続の法定割合に応じて分担する(例:兄弟2人で1/2ずつ)
- 人数で均等に割る(例:3人兄弟なら3等分)
- 経済状況や親との関係性を考慮して柔軟に決める
誰がいくら出すかについては、感情ではなく“合理的な根拠”をもとに冷静に話し合うことが大切です。たとえば「兄は裕福だから多く出すべき」という主張が出た場合でも、相手に納得感がなければ、かえって不満やトラブルのもとになってしまいます。
葬儀費用に関しては、事前にしっかり合意を得ておくことが、家族関係を壊さないためのポイントです。
費用トラブルを防ぐには?
親の葬儀費用をめぐって、兄弟や親族との間にトラブルが起こるケースは少なくありません。「誰がいくら出すのか」「支払いのタイミング」「何にいくら使われたのか」が不明瞭なままだと、不信感につながってしまいます。
こうしたトラブルを防ぐには、事前の話し合いと情報の共有が何より大切で、以下のような工夫が有効です。
- 見積もりや領収書を全員に共有する:何にいくらかかったかの透明性を確保
- 費用分担の合意はできれば書面に残す:LINEやメールでもOK
- 支払う人・立て替える人を明確にする:あとから「払っていない人に請求された」とならないように
お金の話はデリケートですが、遠慮せず、早めに話すことが家族関係を守る第一歩です。モヤモヤを抱えたまま進めると、葬儀後にわだかまりが残る原因になってしまいます。
また、あらかじめ喪主や代表者が「こういうふうに話を進めておくね」と声をかけておくと、親族同士の信頼関係も保ちやすくなります。
相続財産から支払える場合もある
親の葬儀費用は、場合によっては遺産(相続財産)から支払うことも可能です。民法上、葬儀費用は「被相続人の債務」とされ、遺産の中から支出しても法律上は問題ありません。
たとえば、故人の預金や現金が残っていれば、そこから葬儀費用を支払うことで、兄弟間の負担を平等にしやすくなります。
ただし、遺産分割協議が終わる前に一部の相続人が勝手に遺産を使ってしまうと、「使い込み」や「不公平な支出」とみなされるリスクもあります。
トラブルを避けるためには、以下のような点に注意しましょう。
- あらかじめ相続人全員の同意を得てから支出する
- 領収書や明細を必ず保管し、後で共有できるようにする
- 可能であれば、支出の内容を書面で記録しておく
なお、相続税の申告時にも「葬儀費用」として控除が可能な項目があります。相続財産の扱いに迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
費用負担をめぐって兄弟と揉めたら
「自分は出す気がない」「そっちが勝手に決めたことでしょ」など、葬儀費用の分担をめぐって兄弟間でもめるケースは意外と多くあります。特に、事前の話し合いや確認が不十分なまま支払いが発生すると、不満や誤解が生まれやすくなります。
よくあるトラブルの例は、以下のようなケースです。
- 費用を出さない兄弟と連絡が取れない
- 「長男だから出すべき」と一方的に負担を押しつけられる
- 事後報告で請求され、納得できない
このような場合は、まずは冷静に状況を整理し、言った・言わないにならないように証拠や記録をもとに話し合いを行いましょう。感情的にならず、「どうしたら納得できるか」を軸に対話することが大切です。
話し合いで解決が難しい場合には、家庭裁判所の調停や弁護士への相談も視野に入れるとよいでしょう。費用はかかりますが、関係がこじれてしまう前に、第三者を交えて整理することで、スムーズに収束するケースもあります。
葬儀という大切な場面をきっかけに家族関係が壊れてしまわないよう、早めの共有・確認・記録を意識することがトラブル予防の鍵です。
親の葬儀にかかる費用の相場
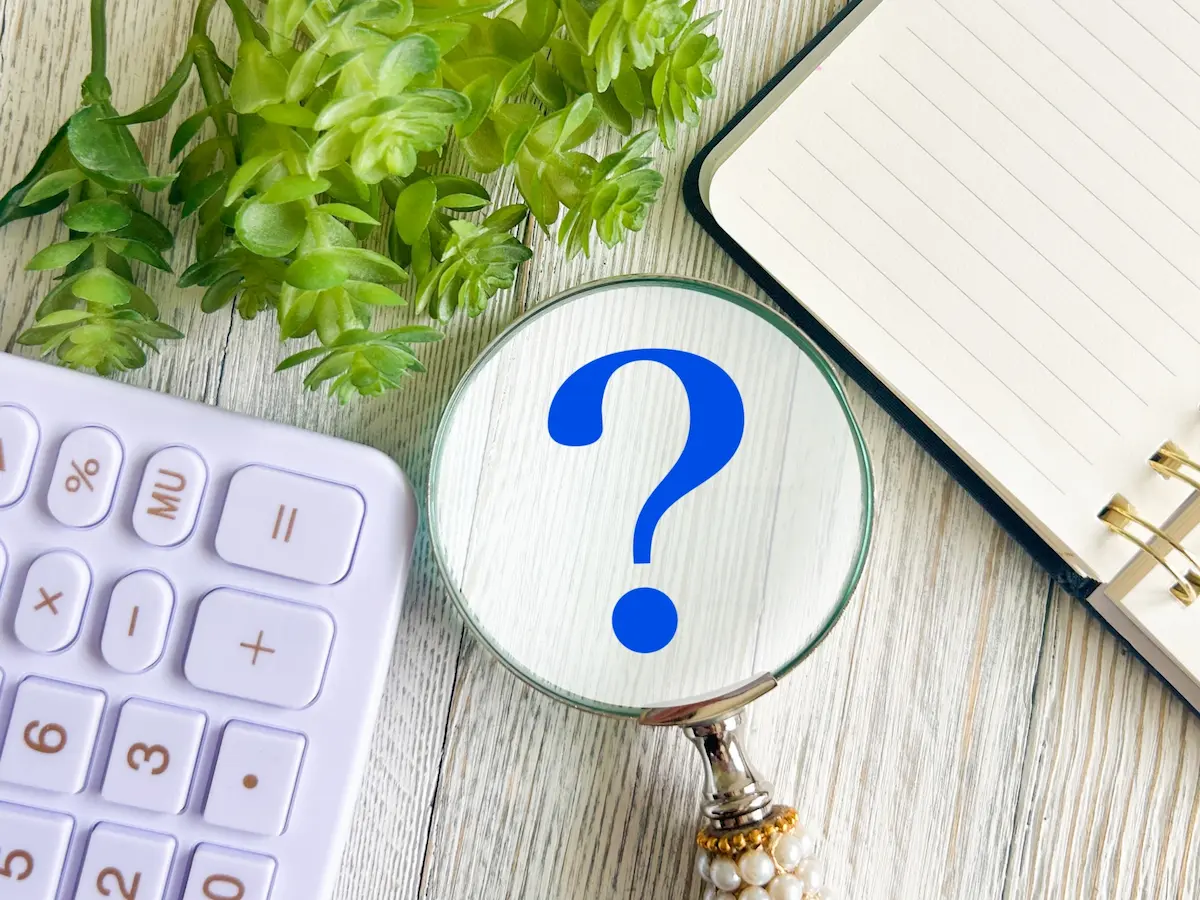
全国平均の費用目安
親の葬儀にかかる費用は、全国平均でおおよそ100万円〜150万円とされています。ただし、この金額は葬儀の形式や規模、地域、参列者数によって大きく変動します。
特に一般葬では、式場費用や人件費、飲食接待費、返礼品費、宗教者へのお布施など、さまざまな項目が重なり、高額になる傾向があります。
形式別の費用比較
葬儀にはいくつかの形式があり、それぞれ費用の目安が異なります。以下に代表的な形式ごとのおおよその相場をまとめました。
- 直葬・火葬式(火葬式):15万〜30万円
- 家族葬:50万〜100万円
- 一般葬:100万〜150万円以上
直葬は最も費用が抑えられる一方で、宗教儀礼や会食などを省略するため、形式として受け入れられるかどうかは家族内での話し合いが必要です。
費用が高くなる要因・安くなる要因
葬儀費用が高くなる主な要因には、以下のようなものがあります。
- 参列者の人数が多く、式場を大規模にする必要がある
- 飲食や返礼品を充実させる
- 位の高い戒名をつける
- 高額な祭壇や棺を選ぶ
逆に、以下のような工夫で費用を抑えることも可能です。
- 少人数で行う家族葬や直葬を選ぶ
- 会食や返礼品の内容をシンプルにする
- 公営の火葬場を利用する
- 事前に複数の葬儀社から見積もりを取る
費用の内訳と項目ごとの目安

葬儀費用と一口にいっても、実際にはさまざまな項目が含まれており、それぞれに金額の目安があります。どの部分にどれだけかかるのかを把握しておくことで、不要な出費を避け、予算に応じた葬儀を選ぶことができます。
葬儀基本費用(式場使用料・人件費など)
葬儀社に支払う基本的な費用には、祭壇の設営、葬儀運営スタッフの人件費、会場使用料、棺や骨壺などの備品代が含まれます。費用は規模やプランによって異なりますが、30万円〜70万円前後が一般的です。
飲食接待費(通夜振る舞い・精進落とし)
通夜や告別式後に行う会食にかかる費用です。参列者の人数に応じて変動し、1人あたり3,000円〜6,000円が目安です。例えば30人分の料理を用意する場合、10万円前後になることもあります。
返礼品費(香典返し)
香典返しとして用意する品物の費用も、葬儀費用に含まれます。相場は香典額の半額〜3分の1程度。参列者全員分を用意すると、5万円〜15万円程度になることもあります。
北海道では葬儀当日に即返しとすることが一般的で、香典額に関わらず1人当たり1000円~が相場です。ただし、高額な香典をいただいた場合は、後日改めて香典返しを送るケースもあります。
宗教者へのお礼(お布施など)
僧侶や神職へのお布施・お礼には明確な料金設定がないため、悩む方も多い項目です。仏式の場合、通夜・葬儀・初七日で20万円〜50万円程度が目安とされています。
火葬料・火葬場使用料
火葬場の使用料は、自治体によって大きく異なります。公営火葬場の場合は無料〜2万円程度、民間の場合は5万円〜10万円程度になることもあります。地域差が大きいため、事前に確認しておくと安心です。
葬儀形式による費用の違い
葬儀には複数の形式があり、それぞれにかかる費用や内容が大きく異なります。どの形式を選ぶかによって、必要な準備や負担額が変わるため、事前に特徴を把握しておくことが大切です。
直葬(火葬式)の費用相場と特徴
通夜や告別式を行わず、火葬のみを行うシンプルな形式です。宗教者を呼ばないケースも多く、必要最低限の費用で葬儀を執り行いたい方に選ばれています。
費用相場:15万〜30万円
ただし、菩提寺(お付き合いのあるお寺)がある場合、直葬(火葬式)を行うことで、後々トラブルにつながるケースもあります。自分では菩提寺はないと思っていても本家がお付き合いしているといったケースもあるため、まずは菩提寺の有無を確認し、直葬が可能かどうか調べる必要があります。
また、儀式を省くことに抵抗を感じる家族もいるため、事前に親族間で十分に話し合うことが重要です。
家族葬の費用相場とケース例
親族やごく親しい人だけで行う、少人数の葬儀スタイルです。通夜や告別式は行うものの、一般参列者を招かないため、接待や返礼品の費用を抑えることができます。
費用相場:50万〜100万円
「静かに見送りたい」「余計な気遣いをしたくない」と考える方に選ばれており、最近では主流になりつつあります。
一般葬の費用相場とよくある流れ
従来の標準的な形式で、通夜・告別式を行い、参列者も多くなる傾向があります。香典返しや会食の数も多くなるため、全体的な費用が高くなることが一般的です。
費用相場:100万〜150万円以上
会社関係や地域の人など、多くの方に感謝を伝えたい場合には適していますが、準備や対応にかかる手間とコストは大きくなります。
親の葬儀費用を抑えるポイント

親の葬儀は大切な儀式である一方で、突然の出費に悩む方も多いものです。必要な部分にはしっかりと費用をかけつつ、無理のない範囲でコストを抑える工夫をすることも大切です。ここでは、葬儀費用を抑えるために知っておきたいポイントを紹介します。
セットプランを活用する
多くの葬儀社では、祭壇・棺・会場費などが含まれたセットプランを用意しています。個別に手配するよりも費用を把握しやすく、見積もりが明確になるというメリットもあります。内容と価格のバランスを見ながら、必要なものが含まれているかを確認することが重要です。
式場や火葬場の選び方を工夫する
公営の火葬場や葬儀会館を選ぶと、民間施設よりも費用を大きく抑えられる場合があります。地域によっては、住民であれば無料または低額で利用できる火葬場もあります。
不要なオプションの見極め
祭壇のグレードアップや高級棺、花の追加装飾など、オプションが多く提案されることもありますが、必ずしもすべてが必要なわけではありません。「見栄」や「なんとなく」で選ばず、故人や家族の意向に沿った形を優先しましょう。
事前相談・見積もり比較の重要性
時間に余裕がある場合は、複数の葬儀社に事前相談をして見積もりを比較することも大切です。費用だけでなく、サービス内容や対応の丁寧さを比較することで、満足のいく葬儀を適正価格で行うことができます。
親の葬儀費用の支払い方法とタイミング

葬儀費用は金額が大きいため、「どのように支払えばいいのか」「いつまでに支払えばいいのか」が気になる方も多いでしょう。ここでは、一般的な支払い方法やタイミングについて解説します。
現金・クレジットカード・葬儀ローン
支払い方法は葬儀社によって異なりますが、現金払いのほか、クレジットカード払いや葬儀ローンに対応している場合もあります。
現金払いは手続きがシンプルですが、短期間でまとまった金額を用意する必要があります。クレジットカード払いであればポイントが貯まるメリットもありますが、利用可能なカード会社や上限額を事前に確認しておきましょう。葬儀ローンは分割で支払える反面、金利や審査がある点には注意が必要です。
支払いのタイミング
多くの葬儀社では、葬儀が終わった後に請求書を発行し、数日〜1週間以内に支払うケースが一般的です。ただし、式の前に一部前金を求められる場合もあります。
急な支払いが不安な方は、事前相談の段階で「いつ、どのように支払うのか」を確認しておくと安心です。
分割払いの可否と注意点
一部の葬儀社では、分割払いに対応している場合もあります。ただし、対応しているプランが限られていたり、金利や手数料が発生することもあるため、契約前に必ず詳細を確認しましょう。
また、クレジットカードの分割払いを利用する場合も、カード会社のルールに従った支払いとなるため、利用限度額や支払い回数をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
親の葬儀費用に使える補助金・給付金
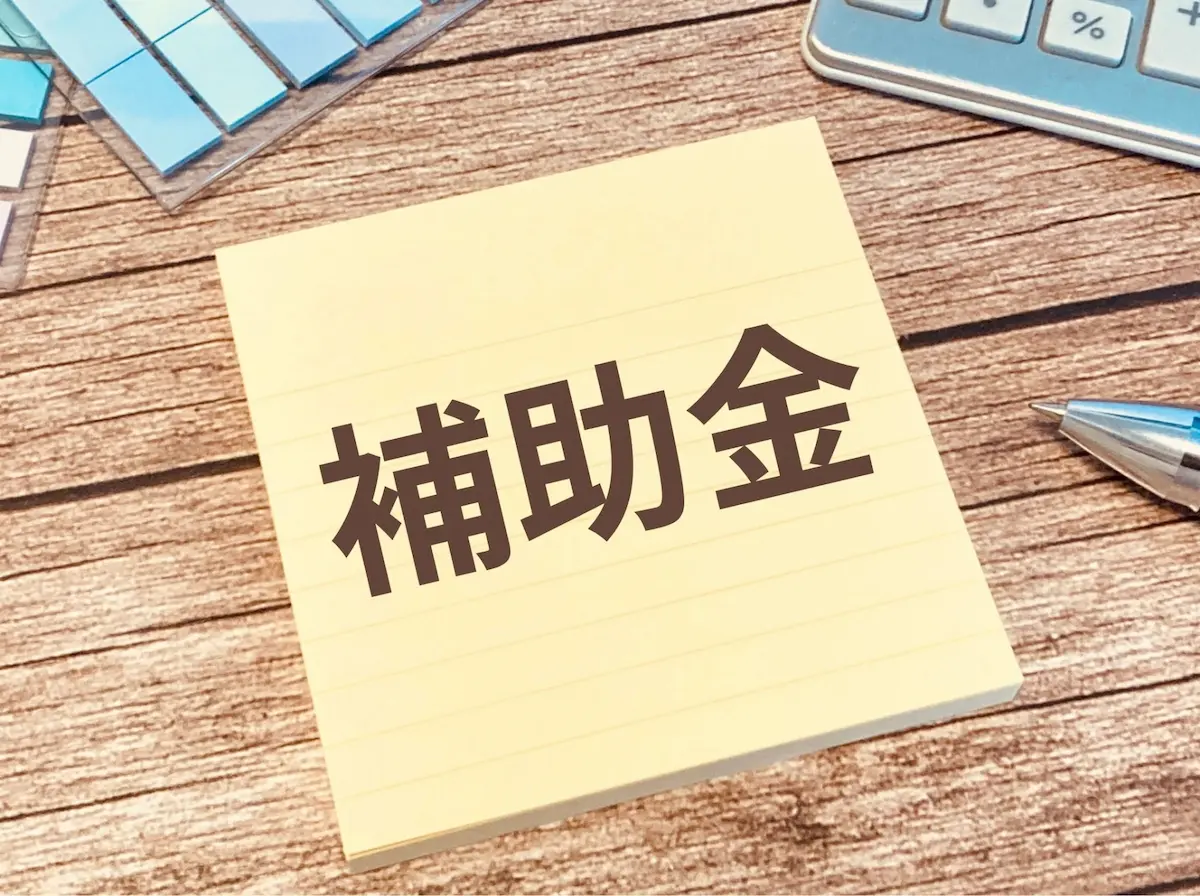
葬儀にかかる費用の一部を補助してくれる制度があることをご存じですか?国や自治体、勤務先の福利厚生制度などを活用すれば、費用負担を軽減できる場合があります。ここでは、主な補助制度について紹介します。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の「葬祭費」
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った人(喪主など)に対して「葬祭費」または「葬祭の給付金」が支給されます。
支給額は自治体によって異なりますが、多くの地域で3〜7万円程度です。申請には、死亡診断書の写しや領収書、本人確認書類などが必要となるため、早めに役所へ確認しましょう。
㈱服部がある北海道余市町では、被保険者が亡くなった場合、喪主など葬儀を行った方に3万円が支給されます。
【出典】北海道余市町ホームページ|保険の給付
勤務先の福利厚生・共済制度
会社員や公務員だった場合、勤務先の共済制度や福利厚生で埋葬料や葬祭費が支給されることがあります。金額や条件は企業ごとに異なるため、故人の勤務先または退職後の所属先に確認してみるとよいでしょう。
生命保険の死亡保険金
故人が生命保険に加入していた場合、受取人に死亡保険金が支払われます。この保険金を葬儀費用に充てることができるため、まずは保険証券や加入状況を確認することが大切です。
ただし、保険金が支給されるまでに時間がかかることもあるため、一時的な立て替えが必要になるケースもあります。
親の葬儀費用に関するよくある質問(FAQ)
- Q. 親の葬儀費用の全国平均はいくらくらいですか?
- A. 一般的に100万〜150万円前後が目安です。形式や地域によって差が出ます。
- Q. 喪主が葬儀費用を全額負担しなければならないのですか?
- A. 喪主が全額払うという決まりはなく、兄弟姉妹などと分担するケースも多くあります。
- Q. 費用をできるだけ抑えるにはどうしたらいいですか?
- A. 葬儀形式を吟味し、不要なオプションを省くことで、コストを抑えやすくなります。
- Q. 補助金や給付金などの制度は利用できますか?
- A. 条件を満たせば、自治体の葬祭費支給制度や生命保険の死亡保険金などが活用できます。
まとめ|親の葬儀費用は誰が払う?「比較」と「備え」で安心

親の葬儀費用については、まず「誰が払うのか」という点をはっきりさせておくことが重要です。喪主が全額負担しなければいけないという決まりは無く、兄弟姉妹などの相続人が話し合って分担するケースも多くあります。トラブルを防ぐためにも、費用の見積もりや支払い内容を事前に共有し、合意を取っておくことが大切です。
親の葬儀は、葬儀の形式や規模によって、かかる費用が大きく異なります。火葬料やお布施、会食費、返礼品などの内訳を把握し、必要以上にお金をかけずに後悔のない葬儀を行うためには、情報収集と比較が欠かせません。
また、補助金や給付金、生命保険の活用によって費用負担を軽減できる場合もあります。利用できる制度についてもあらかじめ確認しておきましょう。
「何も決まっていない状態」で慌てて業者を選ぶのではなく、事前相談や複数社の見積もり比較を行うことで、安心して大切な別れの場を迎えることができます。
㈱服部では、葬儀の事前相談を無料で承っておりますので、ご両親のご葬儀についてわからないことやご不安なことがございましたら、メールやお電話でご相談ください。
▼①お名前 ②フリガナ ③ご住所をご入力のうえ「送信する」をクリックするだけで、資料をご請求いただけます。
▼㈱服部の斎場や特長についてはこちらをご覧ください。