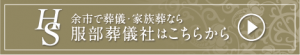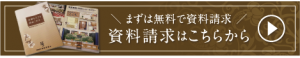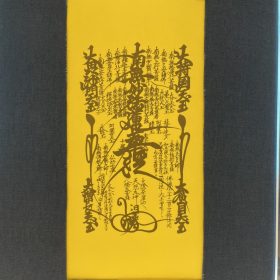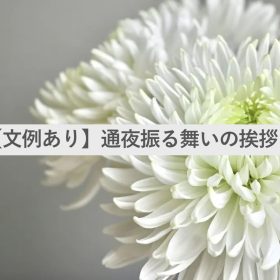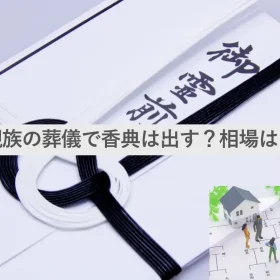大切な家族を亡くした後にひとつの節目となるのが「四十九日」の法要ですが、どのような場所で行うべきなのか迷う方も多いでしょう。
四十九日を行う場所に決まりは無く、自宅や葬儀場で行う方もいれば、伝統的な雰囲気を重んじて「お寺」を選ぶ方もいます。
厳かな雰囲気が漂うお寺には、仏教の教えを身近に感じながら故人と向き合い、丁寧な供養ができるというメリットがあります。
しかしその一方で、移動の手間や費用面への不安をデメリットと感じるケースもあるようです。
今回の記事では、四十九日をお寺で行う背景や準備・持ち物などについて解説していきます。
目次
なぜ四十九日をお寺で行う人がいるのか?

お寺は、仏教の教えを学び修行を重ねる場であると同時に、古くから法要を営む場所としても親しまれてきました。
四十九日は、故人の冥福を祈り、安らかな旅立ちを願う大切な節目とされているため、お寺で行うことに安心感をおぼえる方もいます。
そのような背景から、仏前で読経を受け、故人と向き合う場として、お寺を選ぶことが考えられます。
また、法要のための設備が整っていることも、四十九日をお寺で行う理由の一つです。
四十九日を自宅で行うとなれば、お参りに使う仏具や、参列者のための座布団等の準備が必要になりますが、お寺であればそのような準備は必要ありません。多くのお寺には駐車場があるため、参列がしやすいというメリットもあるでしょう。
四十九日をきっかけに、その後の法要や仏事について相談しやすくなるなど、仏縁を育んでいく意味でも、お寺という場には特別な役割があるのかもしれません。
お寺で四十九日を行うときの主な流れ

お寺によって細かな点は異なりますが、ここでは四十九日法要の主な流れについてご紹介します。
四十九日法要当日の流れ
お寺にもよりますが、四十九日当日は、施主(喪主)は遅くても法要開始の30分前までにはお寺に到着し、僧侶に挨拶をすませて参列者を出迎えましょう。開始10分前には会場にて着席します。
僧侶が開始を告げた後、読経が始まります。故人への思いを胸に、静かにお経を聞きましょう。法要の途中で、「合掌をしてください」「ご焼香をお願いします」といった指示があります。
僧侶が閉式の言葉を述べたら四十九日の儀式が終わります。
当日の詳しい流れは以下の通りです
<四十九日法要・当日の流れ>
- 参列者着席
参列者は法要会場に入場し、着席して会式を待ちます。 - 開式の挨拶・僧侶入場
施主が参列者に対して参列への感謝を伝え、法要開始の挨拶を行います。 - 僧侶読経
僧侶が読経を行います。読経中に参列者は焼香を行います - 僧侶法話・退場
法話終了後、僧侶が退場します。 - 閉式の挨拶
施主が閉式の挨拶をします。
納骨式や会食(お斎)をする場合は、その旨を案内します。 - 納骨式
お墓や納骨堂に納骨する場合は、納骨式を行います。
納骨をしない場合は納骨式も行いません。 - 会食(お斎)
会食を行う場合は会食会場に移動します。
施主は会食開始時と終了時に挨拶をします。 - 閉式
閉式挨拶終了後、施主が参列者に引き物を渡して解散となります。
各席に引き物を用意しておく場合もあります。
会食はどうする?
遺族の考えや地域性によっても違いますが、前述の通り、四十九日法要が終わると会食の場を設けることもあります。
法要後、そのままお寺にて会食をふるまうケースもありますが、場所を移動して別会場で行うことも多いようです。
お寺での四十九日に必要な持ち物リスト

次に四十九日をお寺で行う際に用意する持ち物をご紹介します。
白木位牌
四十九日法要までの“仮”の位牌となる「白木位牌」を持参しましょう。四十九日法要で白木位牌から本位牌に魂を移し、以降は仏壇に本位牌を祀ります。
なお、浄土真宗では位牌ではなく、過去帳を持参します。
遺影写真
一般的に四十九日法要の際は、祭壇に遺影写真を飾ります。参列者が遺影写真を見ることで故人の生前の姿が目に浮かぶため、故人を偲びつつ法要に向き合えるでしょう。
お布施
四十九日法要で僧侶に渡すお布施は、水引のない白い封筒を選ぶ場合が多いのですが、宗派や地域によっても異なるため事前に確認しておくと安心です。
表書きには「お布施」「御布施」と記入しますが、金額相場は寺院や宗派、地域性でも異なります。金額については事前にお寺に確認しておくことで安心感につながります。
お供え物
四十九日法要に欠かせない「果物」「菓子」「花」などのお供え物ですが、こちらもお寺にあらかじめ確認しておきましょう。施主が準備することで、故人に対する供養の気持ちが強まるという意味合いもあります。
「お供えとして不適切なものを持参した」「持ち込み過ぎた」などの失敗をしないよう、持参するお供え物についてはお寺と事前に打ち合わせをしておくことが大事です。
なお、法要当日ではなく、事前にお供え物を持参することを推奨している寺院もあります。
数珠
法要の際は、数珠を手に持ち故人の冥福を祈ります。数珠は持参するのがマナーですが、もし持っていなくても「心を込めて静かに祈る」ことができれば失礼にはあたりません。
ただし、四十九日法要は前もって「行われる時期」が分かっているため、事前に準備しておくのが故人に対する礼儀ともいえます。
また、数珠を忘れたからといって、他の人から借りるのはマナー違反です。忘れてしまった場合は数珠なしで、心を込めて手を合わせましょう。
香典返し
葬儀のときにいただいた香典に対し、お返しの品物を渡すのが四十九日の忌明けのタイミングです。四十九日法要に参列した人に香典返しも渡す場合には、持参しておきましょう。
北海道の香典返しは葬儀当日にお渡しするため、四十九日法要の際に用意するケースは稀ですが、高額な香典をいただいた場合に、香典額の1/2~1/3程度の品を用意することもあります。
引き物
四十九日法要に参列する方は香典を包んできます。その香典に対する引き物も準備しておきましょう。
「会食をする」「会食をしない」「会食はしないけれど折り詰め弁当を持ち帰ってもらう」など、状況によって引き物の金額が異なります。地域の慣習でも異なるため、事前に親戚等に相談するのもよいでしょう。
四十九日法要の服装や香典マナーについて

四十九日をお寺で行うときの服装や香典マナーは、葬儀のマナーと同じなのか異なるのかがわからず、不安を感じる方もいるでしょう。
本章では服装、香典の他に、当日のマナーについてもご紹介します。
四十九日法要は基本的に喪服を着用
四十九日法要は、人が亡くなってから“魂が成仏する”という区切の日でもあります。法要のなかでも大切な儀式ですから、基本的には「喪服の着用」がマナーとなります。
以下の記事では、三回忌までの法要の服装マナーをご紹介していますので、こちらも参考にしてみてください。
【四十九日・一周忌・三回忌…法要・法事はいつまで行うの?種類やマナーも詳しく解説】
香典金額の相場
四十九日を過ぎると故人が“仏”になるため、香典の表書きは「御仏前」が一般的です。仏教の多くの宗派で「四十九日以降」は「御仏前」ですが、浄土真宗の場合は「四十九以前」も「御仏前」です。
また、香典の金額は故人との関係性で相場が異なります。
<四十九日法要の香典相場>
- 親や兄弟などの近親者…1~3万円
- 親戚…5千円~1万円
- 友人や職場の関係…3千円~1万円
当日の注意点とマナー
四十九日をお寺で行う際、当日の注意点とマナーを簡潔にご紹介します。
時間を守って到着する
当日は時間に遅れることがないように、移動時間に余裕を持ちましょう。
施主が遅れてしまうことは、お寺に対しても参列者に対しても失礼にあたります。
持ち物の準備は前日にすませる、道に迷わないように事前に確認しておくなどの対策をして、当日に備えるとよいでしょう。
携帯電話のマナー
法要中に音が鳴り響くことは、故人や遺族に対しても失礼にあたります。突然大きな音が鳴ると、せっかくのお寺の荘厳な雰囲気が壊されてしまうこともあるでしょう。電源を切る、あるいはマナーモードにして音が鳴らないように配慮しましょう。
マナーモードの場合、振動が周囲に伝わることもあります。「サイレントモード」に設定しておくと、法要中でも安心です。
参列席についたら静かに待つ
法要会場で着席し、僧侶が入場するのを待つ間に、席の周囲の人と話をすることもあるかと思います。話すことが悪いわけではありませんが、法要の場であることを意識して、控えめな声で話しましょう。また、僧侶の読経が始まったら会話をやめ、静かに節度を持って参列することが大事です。
四十九日法要をお寺でする際のよくある質問
Q1. 四十九日法要をお寺でする場合、どのくらい前に予約すればいいですか?
<>A. お寺の予定や僧侶の都合によっては希望日に行えないこともあるため、できるだけ早めに相談・予約するのが安心です。葬儀の際に相談する方も多くいます。遅くとも四十九日の1ヶ月前には連絡をしておきましょう。お布施や持ち物の相談もこの時に行うとスムーズです。
Q2. お寺での四十九日は、何人くらいまで参列できますか?
A. お寺の本堂や法要室の広さによって異なります。10~30名ほどの参列が可能なところもあれば、100名まで可能なお寺もあります。人数が多い場合や少人数で行いたい場合は、あらかじめお寺に確認しておきましょう。
Q3. お寺での法要と葬儀会館での法要、どちらが費用を抑えられますか?
A. 費用は内容や施設、地域によって異なります。お寺での法要は「お布施+会場使用料」がかかるケースがあり、葬儀会館では「法要プラン」が用意されていることがあります。どちらが安いとは一概にいえないため、事前に確認することをおすすめします。
Q4. 四十九日法要に参列する際の服装は、平服でもいいですか?
A. 四十九日は重要な法要のため、基本的には喪服が正式とされています。ただし、「家族のみで簡素に行う」と事前に知らされている場合は地味な平服でも差し支えないことがあります。迷う場合は施主に確認すると安心です。
Q5. お寺に法要の相談をする際に、何を聞けばいいですか?
A. 以下の点を確認するとよいでしょう:
-
日時の希望が通るか
-
会場の収容人数
-
お布施の目安や表書き
-
会食の可否(持ち込み・仕出しなど)
-
お供え物の種類と量
-
駐車場の有無
これらを事前に確認することで、当日スムーズに進行できます。
迷ったらどうする?相談先とまとめ
四十九日法要をお寺で行うメリットは、「日本古来の伝統的な形式で供養ができること」や「厳かな雰囲気で故人を偲ぶことができる」といったものがあります。今回は四十九日法要をお寺で行うときに用意するものもお伝えしました。
「何を持参するのか」や「お布施の金額」などについては、お寺に直接確認するのが確実です。
また、四十九日法要をお寺で行う以外にも「自宅」や「葬儀場」などの選択肢があります。故人と縁のある人を多数お呼びする場合、自宅ではスペース的に難しく、準備も大変です。その場合、葬儀会社のホールを利用した四十九日法要を行うという方法もあります。
葬儀社のホールで行うメリットは、会食や引き物の準備など法要に関する一連の流れを事前にしっかり相談できることです。
服部葬儀社にも法要専用ホールがございますので、四十九日法要を行う際のご不安やご質問などお気軽にご相談ください。
▼㈱服部の斎場や特長についてはこちらをご覧ください。
▼①お名前②フリガナ③ご住所を入力し「送信する」をクリックするだけで、資料をご請求いただけます。