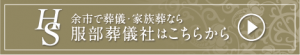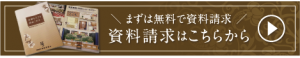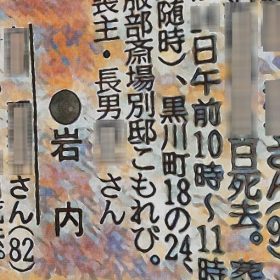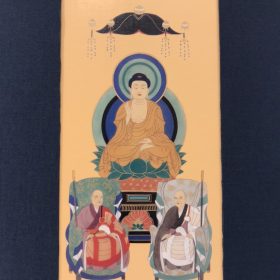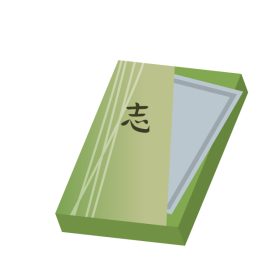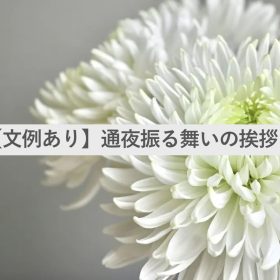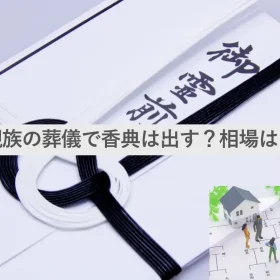通夜のあとに行われる「通夜振る舞い」は、参列してくださった方々へ感謝の気持ちを伝えるために設けられる大切な場です。食事を共にしながら故人を偲び、弔意を分かち合う時間は、遺族にとっても心を支えるひとときとなります。かつてはほとんどの地域で当たり前に行われてきましたが、近年は葬儀の簡略化や生活スタイルの変化によって多様化が進んでいます。
そのような状況の影響を受けてか、最近は「通夜振る舞いは必ず必要なの?」「どこまで声をかければいいの?」といった疑問を抱く方が増えてきました。さらに、当日の挨拶の仕方や、参加を辞退する場合のマナーなど、細かい部分に関する戸惑いの声も多く聞かれます。
本記事では、通夜振る舞いの意味や役割、基本的なマナー、最近の傾向や省略する場合の考え方などを分かりやすく解説します。これから葬儀の準備を進める方はもちろん、参列する立場の方にもお役立ていただける情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
通夜振る舞いとは?

まずは通夜振る舞いの基本的な意味や役割について確認してみましょう。単なる食事ではなく、参列者への感謝を表す大切な場として位置づけられてきた背景や、地域ごとの違いについて解説します。
通夜振る舞いの意味と役割
通夜振る舞いとは、通夜のあとに参列者への感謝の気持ちを表すために行われる食事の席のことです。
遺族が「本日はご多忙の中、故人のために足を運んでいただきありがとうございます」という思いを込めて設けるものであり、故人を偲びながら参列者同士が思い出を語り合う時間でもあります。
この場は単なる食事会ではなく、弔意を分かち合う儀礼的な意味合いが強いのが特徴です。遺族にとっては悲しみの中で一息つく場となり、参列者にとっては遺族の労をねぎらいながら故人を偲ぶ大切な時間となります。そのため料理の豪華さよりも「心を込めてもてなす」という姿勢が重視されるのが一般的です。
また、通夜振る舞いは地域や宗派により慣習が異なることもあります。招く範囲や料理の内容に地域性が現れるため、全国的に統一された形式があるわけではなく、「参列者への感謝を表す食事の場」であることが共通点だと考えると分かりやすいでしょう。
地域や宗教による違い
通夜振る舞いは地域差が大きいため、同じ都道府県内であっても異なる習慣が見られる場合があります。例えば札幌市では、家族や親族のみが参加して会食するのが一般的ですが、同じく北海道の函館市では、食事ではなく乾物などのおつまみやビールを用意して、一般参列者も参加する形式がとられます。
通夜振る舞いは仏教の習わしとして一般的に行われていますが、神道にも「直会(なおらい)」という会食の習慣があります。直会は、仏教の通夜にあたる「通夜祭」が終わった後に行われ、神前に供えた神饌(しんせん)を下げて共にいただくという神事に由来しています。
またキリスト教では、そもそも通夜がないため通夜振る舞いも行う必要がありませんが、日本では仏式の慣習に合わせて、「前夜祭」や「通夜の儀」と呼ばれる儀式や通夜振る舞いを行う場合があります。
このように地域や宗教ごとに形式や意味合いは異なりますが、いずれの場合も共通しているのは「故人を偲び、参列者と思いを分かち合うこと」です。通夜振る舞いの有無や形式にとらわれすぎず、宗教的背景と遺族の思いに沿った形で感謝を伝えることが大切です。
近年の通夜振る舞い
近年では葬儀の小規模化や感染症の影響などにより、通夜振る舞いの規模を縮小したり、簡略化する家庭が増えてきました。かつてのように大人数で長時間行う形式は減少傾向にありますが、それでも「参列者に感謝を伝えたい」という遺族の気持ちは変わりません。そのため、短時間で区切る形や少人数で行う形など、規模を調整しながらも通夜振る舞いを続ける家庭が多く見られます。
通夜振る舞いとは「参列者と食事をともにする場」だけでなく、「感謝の気持ちを表す方法のひとつ」と位置づけられています。
通夜振る舞いの基本マナー

通夜振る舞いには、料理の内容や挨拶の仕方、誰を招くのかといった細かなマナーがあります。この章では、よくある迷いどころを整理しながら、遺族も参列者も安心できる基本のルールを紹介します。
料理や飲食の内容
通夜振る舞いで用意される料理は、地域や斎場の設備によってさまざまですが、基本的には「軽く食事ができる程度」のものを用意します。代表的なのは寿司、煮物、天ぷら、サラダ、オードブルなどで、複数の料理を大皿に盛って参列者が自由に取り分ける形式が一般的です。北海道や東北の一部地域では刺身や寿司が豪華に並ぶこともあり、まるで宴会のように見える場合もありますが、あくまで目的は参列者への感謝を表すこと。料理の内容よりも「心を込めて用意されているか」が大切といえます。
料理を選ぶ際には、参列者の年齢や地域の慣習にも配慮が必要です。例えば、高齢者が多く参加する場合は和食中心のメニューにする、小さな子供が参加するのであれば、子どもでも食べやすい料理を用意するなどの心配りをするとよいでしょう。地域性を熟知している葬儀社であれば、通夜振る舞いの慣習についても詳しい場合が多く、最近の傾向を教えてもらえるので、迷ったら専門家に確認することをおすすめします。
挨拶の仕方
通夜振る舞いで意外と迷うのが「挨拶」です。喪主、あるいは喪主に準ずる立場の人(親族代表など)が最初に一言述べるのが一般的です。長い挨拶は不要で、参列者への感謝を簡潔に伝えるのがポイントです。
例えば「本日はご多用の中、故人のためにお越しくださいまして誠にありがとうございます。ささやかではございますが、食事の席を用意しましたので、どうぞお召し上がりください」といった短い言葉で十分です。堅苦しく考える必要はなく、「故人のために来ていただいた感謝」を一言述べれば、気持ちは伝わります。
挨拶は形式よりも誠意が大切です。遺族にとっては辛い場面ですが、短くても心のこもった一言があれば、参列者に感謝の思いを伝えることができます。
挨拶のタイミングや避けるべき言葉など、通夜振舞いの挨拶について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事】|【文例あり】通夜振る舞いの挨拶|遺族・喪主・参列者の立場別マナーも解説
誰が参加するのか
通夜振る舞いに参加する範囲は地域によって異なります。
関東では参列者全員が通夜振る舞いに参加することが一般的で、家族や親族だけでなく、一般の参列者も招かれます。そのため、通夜に参列する人が多ければ、通夜振る舞いの参加者も大人数になる傾向にあります
関西や北海道では家族や親族のみが参加することが多いため、関東に比べると小規模な通夜振る舞いとなります。
ただし、北海道の一部地域では、一般の参列者も参加することが通例となっているなど、同じ都道府県の中でもしきたりが異なる場合もあります。
一般的には地域の慣習に合わせて行いますが、故人やご家族の意向を優先するケースもあり、必ずしも地域の慣習を守らなければいけないわけではありません。
通夜振る舞いの席に参列するかどうかは、葬儀の際の案内を聞いて判断しましょう。自身が参加範囲に含まれる場合、一般的には極力参加することが推奨されていますが、仕事の都合や体調不良などの理由があり参加が難しい場合は、無理をする必要はないでしょう。
喪主側が参加者の範囲を決めるときは、地域の風習を確認するだけでなく、「参列者への感謝を伝える」ことを基準に考えることをおすすめします。無理に広げたり絞ったりするよりも、その地域で一般的に行われている範囲を参考にしながら、故人や遺族の希望も取り入れることで、自然な形で感謝の気持ちを伝えることができます。
最近の傾向と変化

近年、通夜振る舞いの形は大きく変化しています。コロナ禍の影響や葬儀の小規模化によって、会食のあり方は多様化しました。ここでは現代的なスタイルや選ばれる理由について見ていきましょう。
コロナ禍による変化
コロナ禍は通夜振る舞いの形にも影響を与え、一時的に会食を取りやめたり規模を縮小したりといった対策がとられましたが、収束後は再び従来の形が戻りつつあります。特に地方には、「皆で食事を共にすることが弔意を分かち合う上で欠かせない」との考えから、以前からの形式のまま通夜振る舞いを続ける地域も多くあります。コロナ禍を経ても通夜振る舞いの本質は変わらず、地域の慣習や遺族の思いに合わせて工夫しながら続けられているのが現状です。
簡略化・少人数化の流れ
葬儀全体の傾向として、小規模化・簡略化が進んでいます。家族葬が増えたことで、通夜振る舞いの対象もごく限られた親族や近しい人だけに絞られることが多くなりました。
また、費用を抑えるために通夜振る舞いを縮小して行うというケースもあります。大勢の参列者がいる場合、料理や飲み物を人数分準備すると、数十万円の費用がかかる場合もあり、遺族の負担が大きくなるためです。近年は「無理のない範囲で感謝を伝える」という考え方が浸透しつつあり、簡略化は社会的にも受け入れられる傾向が強まっています。
ただし、地域の風習や親族の慣例に従い、「従来通りの通夜振る舞いを行うべき」と考える人もいるため、通夜振る舞いの形式については、事前に親族間で話し合うことをおすすめします。
現代における通夜振る舞いの意味
このように形は変わっても、通夜振る舞いの本質は変わりません。どのような形式であっても「参列者への感謝の気持ち」を伝えることや、故人と最後の時間を過ごすことが最大の目的です。
通夜振る舞いは儀式的な意味を持ちながらも、時代の流れや社会的な背景に応じて変化してきました。これから葬儀を準備する人にとっては「地域の慣習」と「遺族の気持ち」の両方を大切にしながら、自分たちに合った形を選ぶことが求められるといえるでしょう。
通夜振る舞いに関するよくある疑問(FAQ)
本章では、通夜振る舞いを準備する立場・参列する立場、それぞれの疑問にお答えします。通夜振る舞いの際の挨拶や参加者の範囲といった、特に多く寄せられる質問をご紹介します。
Q1. 通夜振る舞いではどんな挨拶をすればいい?
通夜振る舞いでの挨拶は、長くなくても問題ありません。基本的には喪主や遺族代表が最初に「本日は故人のためにお越しいただき、誠にありがとうございます。ささやかではございますが、お食事を用意しましたので、どうぞ召し上がってください」といった短い言葉で十分です。参列者が緊張しないように、感謝の気持ちを伝えることを第一に考えましょう。
Q2. 通夜振る舞いを簡略化してもよい?
通夜振る舞いは本来、参列者に感謝の気持ちを伝える大切な場です。そのため、できる限り会食の席を設けることが望ましいとされています。最近では感染症への配慮や時間の都合などから規模を縮小する家庭もありますが、その場合でも料理や席の配置を工夫することで、参列者に気持ちを伝えることができます。たとえば短時間で終える、参列者が取りやすいように料理を配置するなど、状況に合わせた配慮が大切です。
Q3. 通夜振る舞いを行わないのは失礼になる?
通夜振る舞いは「参列してくださった方へのお礼」として受け止められているため、まったく行わないと驚かれることがあります。地域や慣習によっては「必ず設けるもの」と考える方も多いため、基本的には会食を準備するのが安心です。もし事情により規模を縮小する場合でも、参列者に向けて感謝を伝える一言を添えることで、誠意が十分に伝わります。大切なのは形式そのものよりも、気持ちをどう示すかという点です。
Q4. 通夜振る舞いに参加してもらう範囲は?
参加者の範囲は地域性が強く、はっきりとしたルールはありません。関東では一般会葬者も広く招き入れることが多いのに対し、関西や北海道では親族や親しい人だけで食事をするのが一般的です。会館や葬儀社に確認すれば、その地域の慣習を教えてもらえます。
参列者側は、自身が参加範囲に含まれていれば可能な限り参加するものとされていますが、体調や仕事の都合など、どうしても参加が難しい場合は無理をせずに帰宅しても問題ありません。
Q5. その他によくある疑問
・お酒を出すべきか? → 通夜振る舞いで出されるお酒には「お清め」の意味があるとされており、お酒を用意することが一般的です。少人数で行う家族葬で、お酒を飲む人がいないなどの場合は、用意する必要はありません。
・子ども連れの場合 → 特に問題はありませんが、長時間にならないよう配慮すると安心です。
・費用はどのくらい? → 一般的に2,000円~5,000円程度が相場ですが、地域の風習や家庭の事情等に合わせて対応するとよいでしょう。
まとめ
通夜振る舞いは、参列者に感謝の気持ちを伝えるために設けられる大切な習わしです。形式や料理の内容は地域や家庭によってさまざまですが、共通しているのは「参列してくださった方をもてなす心」を示すことにあります。料理の豪華さよりも、誠意を持って準備し、感謝の気持ちを伝える姿勢が何より大切です。
近年は葬儀の小規模化や社会状況の変化により、通夜振る舞いの規模や進め方には工夫が見られるようになりました。それでも会食の場を通して故人を偲び、参列者と心を分かち合うことは変わらず重視されています。無理のない範囲で準備し、地域の慣習や遺族の思いに沿った形で行うことが望ましいでしょう。
通夜振る舞いをどのように行うか迷ったときは、葬儀社や地域の習わしを参考にしつつ、「参列者に感謝を伝える」という本来の目的に立ち返ることが大切です。そうすれば、遺族も参列者も安心して心を寄せ合う時間を持つことができます。
㈱服部では、葬儀の事前相談を無料で承っております。北海道余市町の通夜振る舞いについて、わからないことやご不安なことがございましたら、メールやお電話でお気軽にご相談ください。
▼㈱服部の斎場や特長についてはこちらをご覧ください。
▼①お名前 ②フリガナ ③ご住所をご入力のうえ「送信する」をクリックするだけで、資料をご請求いただけます。