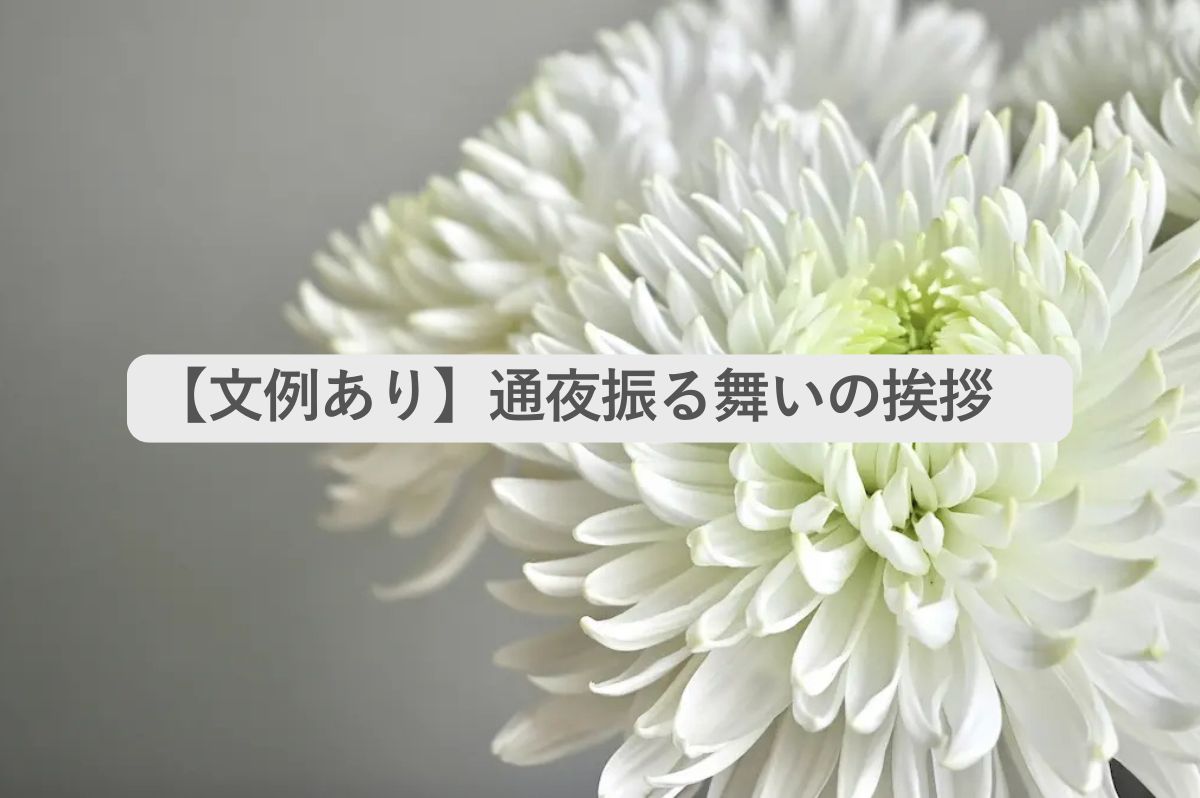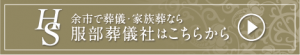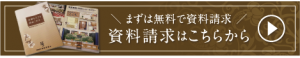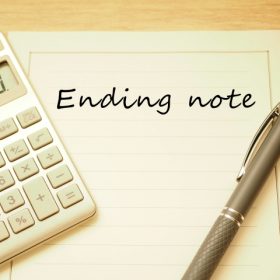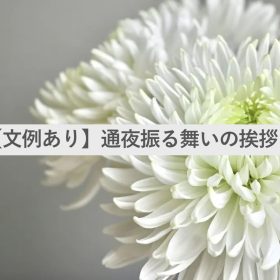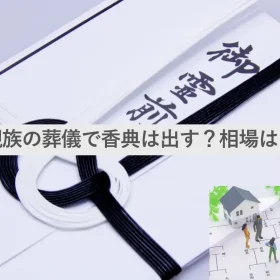「通夜振る舞いの挨拶は、何をどう言えばいいのだろう…」 突然のことで心の準備ができないまま、挨拶の役目を任されたり、遺族として多くの方を迎える立場になったりすると、不安を感じる方は少なくありません。
通夜振る舞いは、故人を偲ぶために設けられた大切な時間で、弔事特有のマナーや言葉遣いがあるため、普段の挨拶とは違った気遣いが必要になります。
本記事では、「遺族・喪主として挨拶する場合」、と「参列者として挨拶する場合」を記載し、立場別に失礼のない挨拶方法をわかりやすく解説します。
そのまま使える挨拶文例や宗派での違い、気をつけたいNG行動まで網羅しているため、このページを読めば通夜振る舞いの挨拶に迷うことはありません。
初めての方でも安心して言葉を選べるよう、短く・丁寧な挨拶のポイントをまとめました。ぜひ最後までご覧ください。
目次
通夜振る舞いの挨拶には実は「明確な正解」がある|まず押さえておきたい基本マナー

通夜振る舞いとは、通夜のあとに参列者へ料理をふるまい、故人を偲びながら労をねぎらう場のことです。地域によって形式は異なりますが、「故人への供養」と「参列者への感謝」の2つが目的である点は共通しています。
通夜振舞いについて詳しくはこちらの記事【通夜振る舞いとは?料理・相場・マナーなど徹底解説】をご覧ください。
この場での挨拶には、長いスピーチや難しい言葉遣いは必要ありません。ただし、弔事の場であるため、普段の食事会とは異なる雰囲気があります。だからこそ、挨拶の内容は「短く・丁寧・気持ちを込める」が基本です。
大切なのは、参列してくれた方への感謝の気持ちを素直に伝えること。これが“正解”と言える挨拶の形です。
この記事では、喪主・参列者の立場別に、今すぐ使える挨拶文例を紹介します。「何を言えばいいのかわからない…」という方でも、このページを読み終えれば安心して挨拶ができるようになります。
喪主・遺族として通夜振る舞いで挨拶するときのポイント
通夜振る舞いで挨拶をするのは、主に喪主やご遺族です。参列者の方々に丁寧な言葉で感謝を伝え、故人との最期の時間を穏やかな空気で過ごしていただくための一言を添えることが大切です。
遺族が挨拶するときに必ず入れるべき3つの要素
遺族としての挨拶では、以下の3つを押さえるだけで失礼のない挨拶になります。
① 参列への感謝の気持ち
② 故人への想いを一言添える
③ 料理に軽く触れつつ、気遣いの言葉で締める
例えば、「本日はお忙しい中、○○の通夜にご参列いただき誠にありがとうございます」と冒頭で述べることで、参列者への感謝を伝えることができます。
長さはどれくらいが正解?話すタイミングと立ち位置
通夜振る舞いの挨拶は「1分以内」が理想です。弔事の場では長い挨拶は避けたほうがよく、短くまとめることで、参列者への負担を減らせます。
挨拶のタイミングは、通夜振舞い開始時と終了時です。会場前方に立ち、参加者全員に聞こえるように落ち着いた声で話すと良いでしょう。
喪主が使える挨拶の文例
ここでは、喪主やご遺族がそのまま使える挨拶の文例をご紹介します。通夜振舞いの挨拶は長々と語る必要はありません。短い挨拶でも十分に気持ちは伝わります。
通夜振舞い開始時
【基本の文例】
「本日はご多忙のところ、○○(故人)の通夜にお越しいただき誠にありがとうございます。 生前は皆さまに大変お世話になり、家族一同、心より感謝申し上げます。 ささやかではございますが、食事をご用意いたしましたので、故人を偲びながらお召し上がりいただければ幸いです。」
【短めの文例】
「本日はお越しいただき誠にありがとうございました。 〇〇も喜んでいることと思います。ささやかではございますが食事をご用意いたしましたので、どうぞお召し上がりください。」
通夜振る舞い終了時
【基本の文例】
「本日はご多用のところ、通夜ならびに通夜振る舞いにご参列いただき誠にありがとうございました。 皆さまと故人を偲び、あたたかな時間を過ごすことができ、家族一同、心より御礼申し上げます。 もう少し〇〇の思い出をお聞かせいただきたいところではありますが、夜も更けてまいりましたので、そろそろお開きとさせていただきます。なお、明日の葬儀・告別式は〇時よりここ〇〇斎場にて執り行います。 ご無理のない範囲でご参列いただければ幸いです。 本日はどうぞお気をつけてお帰りくださいませ。」
【短めの文例】
「本日は通夜振る舞いにご参加いただき、〇〇の思い出話をお聞かせいただいて誠にありがとうございました。 そろそろお開きとさせていただきます。なお、明日の葬儀・告別式は〇時より当斎場にて執り行います。 ご都合がよろしければご参列いただければ幸いです。 皆さまどうぞお気をつけてお帰りください。」
参列者として通夜振る舞いをすすめられたときの挨拶マナー

参列者が通夜振る舞いの席に案内された場合、挨拶をする必要はありません。遺族から直接声を掛けられた場合は「参加させていただきます」など短く丁寧に返事をしましょう。喪主や近親者は多くの対応に追われているため、長話をすることはNGです。
また、通夜振舞いでは喪主が参列者の席を回ってお酌をするケースもあります。その際も、通夜の席であることを忘れず、大声での会話や笑い話、長話は控え、お悔やみの言葉をかけましょう。
通夜振舞いを辞退する場合の丁寧な断り方【文例つき】
通夜振舞いの参加範囲は地域により異なりますが、参加対象となる場合は極力参加するのがマナーです。ただし、体調や仕事の都合で参加が難しいときは、無理に残る必要はありません。その場合も、丁寧な言葉で断るのが礼儀です。
【一般的な断り方】
「お心遣いありがとうございます。あいにく本日は時間の都合により、失礼させていただきます。故人様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。」
【親しい場合の断り方】
「お気遣いありがとうございます。本日はどうしても都合がつかず、ここで失礼いたします。心よりお悔やみ申し上げます。」
ただし、「お冥福をお祈りします」「お悔やみ申し上げます」といったお悔やみの言葉は、宗教や宗派により使うべき言葉が異なるため、次章でわかりやすくご紹介します。
宗教・宗派による挨拶の違い

宗教によって通夜の儀式は異なりますが、通夜振る舞いで喪主が行う挨拶はほぼ同じで、参列への感謝と故人への思いを盛り込むことが基本です。一方、参列者として参加する際に、喪主や遺族にかける言葉は、宗教・宗派によりマナーが異なるため注意が必要です。
| 宗教 | 使われる表現 |
|---|---|
| 仏教 | 「ご冥福をお祈り申し上げます」など一般的な弔事表現で問題ありません。故人を偲ぶ言葉が中心になります。 |
| 神道 | 「ご冥福」という言葉は使わず、「御霊(みたま)の安らかならんことをお祈りします」といった表現が使われます。 |
| キリスト教 | 「安らかなお眠りをお祈りいたします」「天に召された○○様の平安を祈ります」などが一般的です。 |
| 宗派不明の場合 | 無難な表現である「心よりお悔やみ申し上げます」を使用すれば問題ありません。 |
※仏教の中でも浄土真宗では「ご冥福」という言葉を使用しないため、「心よりお悔やみ申し上げます」に言い換えます。
通夜振る舞いで言ってはいけないNGワード・NG行動
通夜振る舞いは故人を偲ぶための食事の場であるため、言葉選びや立ち居振る舞いには注意すべき点があります。悪気がなくても「不適切」と受け取られる可能性がある言動を避けることが重要です。
「楽しい」「おめでたい」など忌み言葉に注意
明るすぎる表現や祝い事を連想させる言葉は避けましょう。特に「楽しい」「にぎやか」「めでたい」などのお祝いごとの連想はNGです。
また、繰り返しの言葉(重ね言葉)も避けるべきとされており、 「重ね重ね」「ますます」「度々」などの表現にも注意しましょう。
過度な思い出話・酒の強要など避けるべき行動
弔事の場では、故人にまつわるエピソードを語ること自体は問題ありません。しかし長く話しすぎたり、場にそぐわない明るすぎる話をすることは控えた方が良いでしょう。
また、酒席であっても「無理にお酒をすすめる」「飲みすぎて迷惑をかける」といった行動は厳禁です。遺族に配慮し、落ち着いた言動をとるよう心がけましょう。
通夜振る舞いの挨拶とセットで知っておきたい関連マナー
挨拶だけでなく、席の座り方や食事の始め方なども知っておくと安心です。最低限のマナーを知っておくことが、遺族や他の参列者への配慮につながります。
席の座り方・料理の手のつけ方
基本的に席は決められていませんが、早めに退席する場合は入口付近に着席するとよいでしょう。喪主挨拶が終わり、飲み物の準備が整った後献杯し、食事を開始します。献杯は乾杯とは違うため、グラスを高く掲げたり、参列者同士でグラスを打ち合わせたりせず、「献杯」と静かに唱和してグラスに口をつけましょう。乾杯では、飲み物を一口飲んだ後に拍手をするケースがありますが、献杯では行わないため注意しましょう。
服装・身だしなみの注意点
基本的に、通夜に参列した服装のまま参加します。ブラックフォーマル(男性はブラックスーツ・女性は冠婚葬祭用のワンピースやアンサンブル)を着用し、ベルトやバッグなどの小物も黒で統一しましょう。
通夜後に個別で挨拶をしたい場合のスマートな伝え方
通夜振る舞いの後に個別で挨拶したい場合は、混雑が落ち着いてから静かに声をかけましょう。 「本日は大変お疲れのところ、ありがとうございました。どうかご無理のないようにお過ごしください。」 など短く挨拶します。
通夜振る舞いの挨拶に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 通夜振る舞いの挨拶は必ずしなくてはいけませんか?
一般的には、喪主または遺族代表が一言挨拶をするのがマナーとされています。ただし地域や宗派によってマナーが異なる場合があるため、迷ったときは葬儀社に確認するか、短い感謝の言葉を伝えるだけでも問題はありません。
Q2. 遺族の挨拶はどれくらいの長さが適切ですか?
通夜振る舞いの挨拶は「30秒〜1分程度」がちょうどよいとされています。長いスピーチは避け、参列へのお礼と故人を偲ぶ一言、そして「ささやかですがお召し上がりください」という案内があれば問題ありません。
Q3. 参列者としての挨拶はどこまで話すべき?
参列者は長い挨拶をする必要はありません。「このたびはご愁傷様でございます」「ご一緒に手を合わせさせていただきます」といった短い言葉で十分です。個人的な思い出話を長く語るのは控えましょう。
Q4. 通夜振る舞いを辞退すると失礼になりますか?
事情があれば辞退しても失礼にはあたりません。その場合は「お気遣いありがとうございます。本日は失礼させていただきます」と丁寧に断るのがマナーです。突然帰るよりも一言添える方が印象が良くなります。
Q5. 会社関係の参列者はどんな挨拶が適切ですか?
会社代表や上司として挨拶する場合は、故人への感謝と遺族への労いの言葉を短く添えます。「生前は大変お世話になりました」「僅かな時間ですがご一緒に偲ばせていただきます」という表現が一般的です。社内の細かい話題や業務内容には触れない方が無難です。
まとめ|通夜振る舞いの挨拶は「短く丁寧」が基本
通夜振る舞いの挨拶では、難しい言い回しや長いスピーチは必要ありません。大切なのは、参列してくれた方への感謝の気持ちと、故人を偲ぶ思いを「短く・丁寧」に伝えることです。立場や地域の違いはあっても、この基本さえ押さえておけば、失礼になることはありません。
遺族や喪主として挨拶をする場合は、「参列へのお礼」「故人への一言」「食事への案内」という流れを意識すると、自然で伝わりやすい挨拶になります。参列者が通夜振舞いの席で喪主や遺族に挨拶する場合は、遺族の気持ちに寄り添い、「心よりご冥福をお祈りします」等、宗教・宗派に合わせた言葉をかけましょう。
一方で、通夜振る舞いの意味や料理の内容、地域差、最近の簡略化の流れなど、挨拶以外にも気になるポイントは多いものです。通夜振る舞い全体の基本を整理したい場合は、「通夜振る舞いとは?料理・相場・マナーなど徹底解説」の記事もあわせてご覧いただくと、全体像がよりイメージしやすくなります。
通夜や葬儀の準備は、限られた時間の中で多くのことを決めなければならず、不安や戸惑いを感じるのが当然です。一人で抱え込まず、地域の慣習に詳しい葬儀社や、信頼できる相談窓口を活用しながら進めていきましょう。丁寧に気持ちを込めて準備をすることで、故人や参列者の心に寄り添った通夜振る舞いになります。
通夜振る舞いの挨拶に迷ったときは、本記事の文例をそのまま使っていただいても問題ありません。
㈱服部では、通夜振舞いに関する疑問など、葬儀全般の事前相談を無料で承っております。北海道余市町の葬儀について、わからないことやご不安なことがございましたら、メールやお電話でお気軽にご相談ください。
▼㈱服部の斎場や特長についてはこちらをご覧ください。
▼①お名前 ②フリガナ ③ご住所をご入力のうえ「送信する」をクリックするだけで、資料をご請求いただけます。