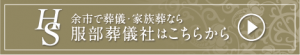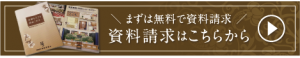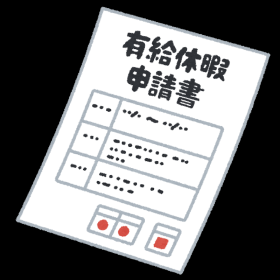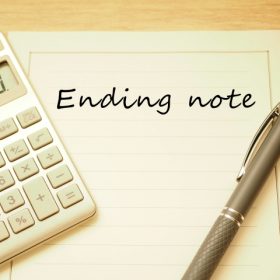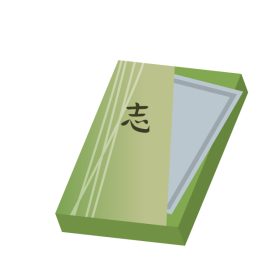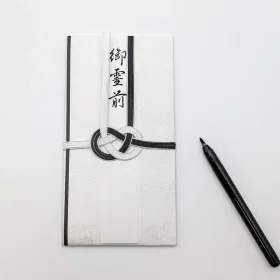昔は「仏間」がある戸建て住宅が多く、仏壇に位牌や仏具を置いたり、仏間の壁面に先祖代々の写真を飾ったりするのが当たり前の光景でした。
しかし最近は、以下のような理由などから、仏壇がない家も増えてきました。
- 引っ越しや建て替えで仏壇を処分した
- そもそも分家で仏壇がない
仏壇がないときの疑問のひとつとして「法要はどこでやるの…?」というものがあるのではないでしょうか。
今回は、昨今の「仏壇なし」の背景とともに、仏壇がない場合の法要に関する疑問を詳しくお話していきます。
目次
そもそも「仏壇」とは?

仏壇は本来、仏様(本尊)をお祀りし、礼拝するための場所であり、小さなお寺のような役割を持っています。しかし近年では、故人を偲び、日々供養する場としての意味合いが強くなっています。
日本では、火葬後のお骨は「お墓への埋葬」や「納骨堂への安置」などの方法で供養されるのが一般的です。命日やお盆、お彼岸など、お墓を訪れる機会は年に数回ありますが、自宅に仏壇を置くことで、供養の場をより身近に持つことができます。
また、仏壇に祀る位牌には故人の魂が宿るとも考えられています。仏壇に手を合わせることで供養になるだけでなく、位牌に宿った魂と対話することで、故人の存在を日々身近に感じながら過ごせるでしょう。
大切な人が亡くなり、その姿を見ることができなくなっても、仏壇を置くことが、故人への感謝の気持ちや懐かしさを感じることにつながります。
仏壇なしの背景とは?
昔に比べて仏壇を置かない家庭が増えているのはなぜでしょうか?
考えられる3つの理由をご紹介します。
- スペース上の問題
- 洋風の家になじまない
- 仏壇じまいをしてしまった
スペース上の問題
仏壇がない家が増えてきた背景には、「仏間が確保しづらい」といった、現在の住宅事情が関係しています。
最近は、物を持たないコンパクトな暮らし方も注目されていることから、新築では平屋や狭小住宅も人気で、大きな仏壇を置くスペースがない住宅も増えています。
また、和室のない賃貸物件や、ワンルームで一人暮らしをしている方は、仏壇を置くためのスペースを確保するのが難しいこともあるでしょう。
洋風の家になじまない
洋風住宅が主流となっている現在では、新築時にあえて和室を設けないケースが増えています。
昔ながらの和風住宅では、畳のある和室に仏壇が馴染んでいましたが、和室のない洋風のインテリアには、仏壇が合わないと感じる方もいるかもしれません。
そのため、部屋の雰囲気に合わせて、大きな仏壇ではなく、置き型のコンパクトな仏壇を選ぶ方も増えています。
仏壇じまいをしてしまった
以前は仏壇を置いていたご家庭でも、「建て替え」や「引っ越し」にともなって仏壇じまいをして、仏壇なしになる場合があります。
建て替えや引っ越しといった居住環境の変化以外にも、供養に対する考え方が変化したことや後継者がいないこと等から、仏壇じまいをする人も少なくないようです。
仏壇なしの家は近年増えている。供養はどうする?

家族が亡くなった後、必ずしも自宅に仏壇を置かなければならないわけではありませんが、仏壇がないことで故人の冥福を祈る機会が減り、大切な家族への思いが薄れてしまうのは寂しいものですよね。
しかし、たとえ仏壇がなくても、「供養したい」という気持ちがあれば、自宅で故人を偲ぶことは可能です。
昔ながらの仏壇を置かずに故人を偲ぶ方法は以下の通りです。
- 位牌や遺影写真で供養する
- 小さな仏壇を置く
位牌や遺影写真で供養する
仏壇を置かなくても、戒名や法名が記された位牌や遺影写真を飾って、故人を供養する方もいます。
「魂が宿る」とされている位牌と違い、遺影写真には宗教的な意味はありませんが、生前の姿を見ることで、日々故人を思い出し、心の中で偲ぶことができます。
ちなみに、浄土真宗では位牌を用いず、「過去帳」や「法名軸」がその役割を果たします。
このように、正式な仏壇がなくても、位牌や写真を飾ることで、日常の中で供養の気持ちを持ち続けることができるでしょう。
小さな仏壇を置く
仏壇と聞くと、伝統的な大きな仏壇を思い浮かべる方も多いでしょう。
“仏壇なし”の家庭が増えている背景には、そのような大きな仏壇を置くスペースを確保できないという問題もありますが、現在では従来とは異なるデザインの仏壇も増えています。
洋風のインテリアに馴染む、スマートでおしゃれなデザインの仏壇や小さな仏壇なども定番となり、仏具店だけでなく、ネット通販で簡単に購入することができるようになっています。
「スペース的に昔ながらの大きな仏壇は置けないけれど、仏壇なしでは寂しい」と感じる方は、洋風仏壇やコンパクトな仏壇を検討してみてはいかがでしょうか。
仏壇なしでも故人への供養の気持ちを大事にするには?
ライフスタイルが多様化している現代は、さまざまな供養の方法があるため、仏壇の「ある・なし」を考える前に、まずは供養する気持ちを大切にしたいものです。
例えば、大きく立派な仏壇を用意したとしても、以下のような対応では、ご先祖様に対して失礼な状況になっているといわざるを得ないでしょう。
- 扉を閉めたままで開けることがない
- お供えをしない
- 仏具にホコリがかぶったまま放置されている
逆に、仏壇がなくても、供養の気持ちが感じられるケースもあります。
- 毎日写真に語りかけている
- お花を飾っている
- お菓子などのお供えをする
写真への語りかけやお供えだけでなく、お盆やお彼岸、命日など特別なときはお墓やお寺に行き、故人の冥福を祈ることも「供養」といえるのではないでしょうか。
仏壇なし!法事・法要はどうするの?

仏壇がなければ、法事や法要はどうするのだろうと不安に思う方もいるかもしれません。
ここでは仏壇がない場合の法事・法要に対する考え方や、仏壇なしで法事・法要を行う方法をご紹介します。
仏壇がなくても節目の法事・法要は大切
仏壇は、お住まいのなかにある“小さなお寺”のような存在で、お寺やお墓に行かなくても自宅で日常的に故人を供養できるところですが、仏壇がなくても、前述したようにさまざまな形で故人を供養し、懐かしむことはできます。
とはいえ、日々の供養とは別に、節目の法事・法要もしっかり行いたいと考えている人は多いでしょう。
家族が亡くなると、一周忌、三回忌、七回忌・・・と法要・法事が続きます。法事は故人に縁のある人が集い、会食をしながら故人のことを語り合う大切な機会であり、改めて故人との繋がりを意識することができる場です。
亡くなった方の供養を通じて新たな縁が生まれることもありますし、仏法に触れることで学びを得ることもあるため、これから生きていく人たちにとっても大切な機会となるでしょう。
仏壇がなくても法事・法要はできる
葬儀では、お寺や斎場などの大きな会場を借りることが一般的ですが、一周忌以降の法要は自宅で行う方もいます。
法要には僧侶による読経が欠かせないことから、自宅で法要を行う場合は仏壇が必要と考える方も多いでしょう。
実際、檀家になっている方は、基本的に仏壇を置いているため、自宅で法要を行えます。
それでは、檀家になっておらず、自宅に仏壇がない場合は、法事・法要はできないのかといえばそうではなく、お寺や葬儀社の会場などで行うことが可能です。
ちなみに、自宅で法事・法要を行う場合は、以下のようなデメリットがあります。
- 人が集まるためのスペースを確保する必要がある
- 準備や片付けに手間がかかる
このような理由から、仏壇のある・なしにかかわらず、法要・法事を自宅以外の場所で行う方も少なくありません。
家族以外の人にも集まってもらいたい場合は、むしろ自宅以外の場所で行った方が集まりやすいケースもあります。
自宅では遠方から来てくれた方のために、近隣に駐車場を確保しなければならない可能性もありますが、斎場等で行う場合は駐車場があるため、喪主や参列者の負担を軽減することができるでしょう。
当社でも、会食を含んだ法事プランをご用意していますので、どうぞお気軽にご相談ください。
北海道余市・後志地区・小樽市・札幌市の法要は(株)服部へ
まとめ
昔は家に仏壇がある住宅も多くありましたが、最近は住宅事情の変化や価値観が多様化していることから「仏壇なし」の家庭も増えてきました。
仏壇なしの家で供養ができるのか…と心配されている方もいらっしゃいますが、重要なのは仏壇があることではなく「供養をする気持ち」です。位牌や遺影を置いて供養をしている方も多いですし、節目の法要を大事にしている方もいらっしゃいます。
筆者の知人のお母様の話になりますが、建て替え時に間取りの関係から“仏壇じまい”をして、古い大きな仏壇を処分したそうです。
仏壇はなくなっても大切な旦那様のご供養をしたいと、現在は写真と過去帳を飾ってお供えをしながら語りかけているとのこと。
先日、そのお母様がふと、「仏壇がないけど、自分が死んだら一周忌とか三回忌に僧侶を呼べないのでは…?」と不安を口にされたそうです。
お母様世代ともなると仏間があるのが当たり前の時代。葬儀はお寺などでやるものの、その後の法要は自宅に僧侶を呼ぶイメージがあるようで「仏壇なし」で今後の供養がご不安になったのかもしれません。
「仏壇がないけど法事をどうしよう」といったご不安を感じられている方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
▼㈱服部の斎場や特長についてはこちらをご覧ください。
▼①お名前②フリガナ③ご住所を入力し「送信する」をクリックするだけで、資料をご請求いただけます。